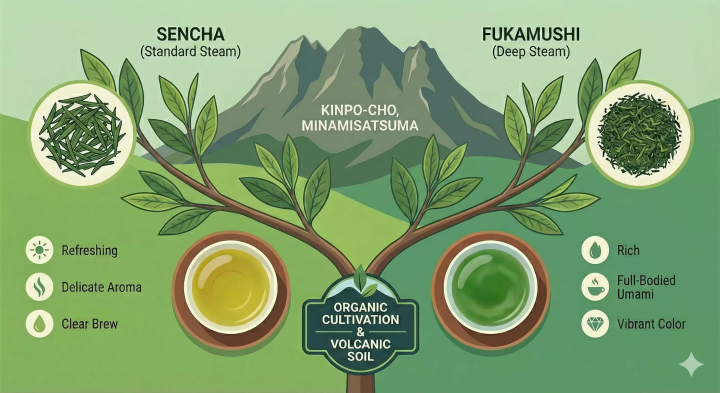古式伝承製法を受け継ぐ「知多の酒蔵」澤田酒造に魅せられて

澤田酒造は常滑焼で知られる愛知県常滑市で、江戸末期(1848年)に創業した歴史ある酒蔵です。代表銘柄は「白老(はくろう)」。蔵名には「お米を丁寧に白く磨く」「お客様の健康長寿を願う」「老練な酒造りを追求する」という想いが込められています。
愛知県にある「知多半島」には魅力がたくさん。そんな知多半島の常滑市にある澤田酒造は、伝統と革新を融合させ、受賞歴のある日本酒「白老」シリーズを製造する酒蔵です。

澤田酒造の社長、澤田薫氏は、名高い日本酒「白老」の酒造りを統括する6代目です。
-
目次
- 常滑の伝統を礎に築かれた酒蔵
- 知多半島の常滑で生まれた蔵人の系譜
- 酒蔵見学と試飲ツアーで、常滑を訪れる
- ささらけ: ローカルの酒蔵で味わう日本酒のテイスティング体験
- 日本酒だけにとどまらない楽しさ
常滑の伝統を礎に築かれた酒蔵

常滑にある澤田酒造の入り口。澤田酒造は1848年に創業した家族経営の酒蔵で、愛知県知多半島の常滑にあります。常滑は、ジブリ映画に出てきそうな趣のある町で、常滑焼の産地でもあります。2007年より、6代目社長の澤田薫氏が酒蔵の指揮を執ります。彼女は、日本で増えつつある女性蔵元(酒造りの最高責任者)の一人です。

澤田社長が酒蔵の施設案内ツアーを先導。澤田酒造の酒造りについて学んだり、常滑焼の酒器コレクション「ささらけ」を使い、地元の食材を使った特製おつまみと合わせ、白老酒の試飲を楽しめるコースもあるので、酒蔵見学は、お薦めです。

「ささらけ」セットを構成する白老の4種の日本酒。それぞれのお酒に、地元の陶芸家がデザインした手作りの酒器が組み合わされます。
澤田酒造の製品の実力は確かなもので、製造技術とお酒の品質において、独立行政法人 酒類総合研究所 が主催する「全国新酒鑑評会」で7回の受賞。2016年には、澤田酒造の梅酒「白老梅」が、全国梅酒品評会が主催する「日本酒梅酒部門」で銀賞を受賞しました。そして、2019年、2024年と継続して受賞しています。
澤田酒造はいかにして、多くの酒蔵が衰退する中、酒造りをこれほどまでの高いレベルに引き上げ、成功をおさめたのでしょうか?
知多半島の常滑で生まれた蔵人の系譜
知多半島における「酒造り」の盛衰と再生

江戸時代(1603年〜1867年)の知多半島では、海運業の発展により、日本酒やたまり、味噌、醤油などの物資をこれまでよりも速く江戸(現在の東京)へ、届けることができたことから、経済の発展に貢献しました。

知多半島は、良質な米と酒造りに欠かせない軟らかい清水の水源、更に蔵人(くらびと。酒蔵で働く人々)と呼ばれる季節労働者にも恵まれていました。明治時代には、この地域は日本第2位の酒の産地となり、澤田酒造も220を超える酒蔵のひとつとなりました。

澤田酒造は、酒蔵から約2キロメートルも離れた丘に湧く清水を創業当初から、私設の水道管で、酒蔵にある井戸までひいて仕込み水としています。この辺りは、 複雑な地質構造で、湧き出ている場所によって水質が変わるという特徴があります。

酒蔵見学に参加したお客様は、澤田酒造の酒造りに使われる美味しい清水の仕込み水を飲ませていただけます。

知多半島は比較的温暖な気候ですが、冬になると”伊吹おろし”と呼ばれる冷たい風が伊勢湾を渡って吹き下ろします。この冷たい伊吹おろしを取り込んで蔵を効率よく冷ますために、この地域の酒蔵では、この自然現象を利用し、北西が角になるように建物が逆L字型に配置されています。

タンクの中で発酵するもろみ。 澤田酒造は、速醸酛と呼ばれる腐造のリスクを軽減する発酵技術の発展において重要な役割を果たしました。

明治維新が大きな変化をもたらし、一大生産地としての知多半島の酒づくりの地位が衰退をみせはじめると、 知多の酒造家たちは生き残りをかけて「豊醸組」という組合を設立し、醸造技術の改良に取り組みます。澤田酒造は、この組合の重要な役割を果たします。自家の蔵に豊醸組指定の試験場をつくり、大蔵省醸造試験所より、江田鎌治郎技師を招き、お酒の腐造を防ぐ画期的な酒母造り方法を研究開発しました。

この革新的な方法は、腐造防止に大きな成果を上げ、醸造家は発酵プロセスを加速させることができました。この技術は急速に普及し、現代の日本酒醸造の礎となりました。
澤田酒造は、その歴史を通じて、新しい技術をいち早く取り入れながらも、手作りの伝統的な醸造技術を守り続けることで発展を遂げてきました。
伝統を守りつつ、革新を続ける酒蔵

シアスター・ゲイツが常滑での滞在中に澤田酒造とコラボレーションした限定酒ボトル。MON Karakara(ゲイツは日本語で門を意味する)は特別に醸造された濃厚で本格的な辛口の日本酒です。

地域の陶芸家とのコラボレーションから世界とのコラボレーションまで発展し、澤田酒造は世界的に有名な現代アーティスト、シアスター・ゲイツ氏ともコラボレーションを行いました。彼は「アフロ民藝」展のために、オリジナルの小ロットの日本酒ボトルをデザインしました。
これらの革新的なアイデアは、常滑の地域文化を日本国内および海外の新たなオーディエンスに紹介し、日本酒そのものに馴染みがなくても、芸術や日本の地域工芸に魅力を感じる人々に知ってもらう新たなきっかけとなるでしょう。
酒蔵見学と試飲ツアーで、常滑を訪れる
昔ながらの伝統的な酒造り

澤田酒造では、酒造りの工程の至る所で、他の酒造会社とは一線を画す伝統的な道具や技術が用いられています。例えば、蒸米には、ほとんどの酒蔵が金属製の蒸米機を採用している中、澤田酒造では甑(こしき)と呼ばれる木製の蒸米機を使い続けています。

この方法には、いくつかの利点と欠点があります。木製の甑は熱を保持するため、温度がゆっくりと上昇し、米をより均一に蒸すことができます。これにより、蒸し米に余分な水分が浸透するのを防ぎ、適切な調湿をすることができます。

一方で、木製の甑は、最新の金属製のものよりも多くの燃料を必要とするため、経済的なコストがかかります。また、修理ができる桶職人の数も減少しているため修理費用もかかります。

澤田酒造では、発酵に必要な麹菌を培養するために「麹蓋」という古くて小さな木箱を使用しています。小型の箱だと少量ずつしか作れないため、酒蔵のスタッフにとっては労働時間が長くなることを意味しますが、彼らは昔ながらのやり方に誇りを持っています。
その理由は納得で、これらの小さな容器を使うことで、バラつきがなく、より均質な麹菌が米に深く食い込んだ「破精込(はぜこみ)」が可能となり、お米の旨みをお酒の中に溶け込ませることができます。
澤田酒造は、愛知県内で唯一、すべてのお酒づくりに麹蓋を使用している酒蔵です。

酒蔵見学で、澤田社長は、英語と日本語の両方で質問に答え、詳しく説明してくれます。これは日本ではめったにない機会です。
ささらけ: ローカルの酒蔵で味わう日本酒のテイスティング体験

澤田酒造は、地元の常滑焼陶芸家4名とコラボレーションし、白老の個性と味わいを引き立てる酒器を制作しました。左から右へ:知多の花露、からから 白老、特別純米酒 白老、純米吟醸熟成酒 豊醸。
澤田酒造は、素晴らしい日本酒を楽しむことは、ただお酒を飲むことではないと考えています。一緒に食べる食事や、お酒を注ぐ器、さらにはそのお酒を造る人々の背景や文化を知ることなど、その体験のすべてが楽しみにつながるのです。 その信念から「ささらけ」が生まれました。 常滑は、伝統的な「常滑焼」の産地として有名です。そこで、この地の陶芸家たちに、日本酒の味と香りを引き立たせるカップのデザインを依頼しました。

それでは、テイスティングで紹介された4種類の日本酒と、ユニークなデザインの酒器について、それぞれ詳しく見ていきましょう。

日本酒の試飲体験「ささらけ」では、酒粕やその他のユニークな発酵食材を使った地元のおつまみも提供されます。
知多の花露

「知多の花露」は、地元知多半島で栽培された山田錦を35%まで磨き、長期低温発酵で醸造した純米大吟醸です。芳醇な米の旨みを残しながらもすっきりとした味わいに仕上がっています。
フレッシュで、甘いイチゴを思わせるようなフルーティーな香りです。この日本酒は、ほのかな甘味と上品な酸味が絶妙な味わいを生み出しています。ラベルに描かれた色鮮やかな赤いサザンカは常滑市の花で、酒米、水だけでなく、全ての原材料が愛知県産であるという、こだわりを象徴しています。
酒器:花露

世界的に有名な陶芸家、加藤真美氏によって、使いやすさを重視してデザインされました。背が高く、上に向かって口がすぼまり、香りを閉じ込めるので、純米大吟醸の香りをより一層楽しめるように工夫されています。
独特な造形の器は、飲む人の手に心地よくフィットするように作られています。それは重心がしっかりとした杯で、ほのかな甘みと酸味の余韻が残ります。
からから

「からから」は、飲みやすいが個性のある辛口の日本酒で、少し温めても冷やしても、飽きずにいつまでも楽しめます。辛口の日本酒らしく、さまざまな料理と合わせやすいのが特徴。
その香りは「潮風が吹き抜けるようなドライフィニッシュ」と表現されており、これは伊勢湾を西に、三河湾を東に臨む知多半島を意識したものかもしれません。
軽やかでなめらかな口当たりで、ほのかに新米の豊かな風味を感じさせます。飲み干した後に感じるキレのある後味は、「潮がひいた後のひんやりとした印象」です。からから(文字通り「辛辛」)は、ドライな後味にほのかな塩味が感じられ、まるで海にいるような感覚を味わえます。
酒器:からから

伝統的な常滑焼の陶芸家、竹内孝一郎氏は、父親である竹内公明氏から学んだ灰釉の技術と沖縄で学んだ技術を組み合わせています。 「潮風の香りが優しく広がるように」と、広口のからからをデザインしました。「波のように」口の中に流れ込み、爽やかで軽やかな印象を与えてくれる杯をテーブルに戻すと、波が引いて砂浜が現れるようなニュアンスを感じられます。
お酒を注ぐと、灰釉が器の表面で明るく輝き、常滑焼特有の粗い質感が、常滑の海岸を想起させると同時に、口当たりに爽やかな辛口の味わいを添えてくれます。
特別純米酒 白老

海を感じさせる青色のラベルに銀色の文字で書かれた「特別純米酒 白老」は、一口飲むごとに米の深い旨みが感じられる、コクのある味わい深いお酒です。この特別純米酒は、60%まで磨いた地元産の酒米「若水」と知多半島の湧き水で作られており、常滑の自然のテロワールと豊かな資源のエッセンスが凝縮されています。
外観は、ほのかに黄色がかった澄んだお酒です。香りは炊き立ての米の香りと、かすかな乳香が感じられます。この地元産の酒米「若水」が、芳醇なまろやかさを与えており、日本酒を初めて飲む方にも飲みやすい味わいでありながら、日本酒通の方にも満足いただけるしっかりとした味わいとなっています。
酒器: 若水

職人の清水小北条氏は、常滑で急須づくりをする家系で育ちました。その血統は、この器の落ち着いた朱色に明確に表れています。手作りの縞模様は、常滑焼らしいクラシックスタイルで、陶芸家によるろくろの安定した回転を彷彿させます。
清水氏は、赤土を釉薬なしで焼くという決断を下しました。これにより、常滑の土に含まれる鉄分が、若水の酒の酸味と絶妙なバランスとなり、よりまろやかな味わいを引き出します。
口当たりの良い形状は、熱燗(温めた日本酒)を飲む際に、口元に優しくフィットし、心地よいまろやかさを引き立てます。
純米吟醸熟成酒 豊醸

2年以上熟成させた豊醸は、口当たりが滑らかで、口いっぱいに広がる豊かな風味が、後味はすっきりとしていながらも、キレのある深い味わい。
ラベルは、種籾や赤みを帯びた豊作の月を思わせる秋らしい色調で、中身を想起させます。
それは、慎重に熟成させることで引き出されるシナモン、生姜、ナッツの力強く芳醇な香りです。「豊醸」は他の白老のお酒よりも濃厚な口当たりで、”黒糖”のような熟成された甘味があります。米の深いコクを放ち、繊細な渋味とバランスが取れた後味は、舌の奥に長く残る滑らかな余韻へと優雅に消えていきます。これは洗練された経験豊かな日本酒愛好家向けにお薦めの、非常に熟成されたお酒です。
酒器:豊醸

陶芸家、谷川仁氏は、知多半島周辺の海で自ら採取した海藻を使用する特別な「藻掛け技法」で知られています。 谷川氏の作品は熟練の技と遊び心がバランスよく組み合わさって、とても魅力的です。その魅力はすべて、この「豊醸」の器にも表れています。
酒器と「豊醸」の濃厚な風味を、どこからでも堪能できるように、縁の形は厚くしっかりとしたものになっています。この変則的な縁のおかげで、飲む人は熟成された豊かな風味を自分好みの方法で楽しむことができます。器の色合いは、時が経つにつれて変化し、使う人それぞれにフィットする「育つ器」です。
実際に、使い込むほどに味わい深い色合いへと変化していきます。約200年前に常滑で生まれた「藻掛け」という陶器づくりの技法により、独特な金色の模様が徐々に浮かび上がってきます。「豊醸」は、遊び心を忘れない成熟した大人たちが長い夜を楽しむために作られた杯であり、お酒です。
日本酒だけにとどまらない楽しさ

きき酒を楽しんだ後は、澤田酒造の品揃え豊富な直営店舗「澤田北倉」をのぞいてみてはいかがでしょうか? 季節限定の「白老」や定番酒の幅広い品揃えが自慢です。

酸味のあるフルーティーなものが好みなら、澤田酒造では知多半島で栽培された地元特有の梅品種「佐布里梅」を使った梅酒も製造しています。「白老梅 純米吟醸古酒仕込みの梅酒」は、2016年と2019年、そして2024年に全国梅酒品評会で銀賞を受賞しました。

江戸時代に書かれた歴史的なレシピ本『本朝食鑑』に記載されている梅酒の製法を忠実に再現したもので、知多で栽培された地元の梅をワラ灰に一晩漬けることで、エグ味やアクを溶かし抜き、全て手作業でヘタを取り除きます。そして、純米吟醸や純米大吟醸の熟成酒に漬け込みます。
この丁寧な工程により、雑味のない爽やかな梅の酸味が効いた、甘酸っぱい梅酒「白老梅」ができあがります。

澤田酒造では、受賞歴のある純米吟醸仕込みの梅酒 白老梅、純米大吟醸仕込みの梅酒 白老梅、白老梅ヌーボーなど、日本酒以外にも梅酒を製造しています。
日本のHAKKO(発酵)はUMAMI(旨味)の源。その知られざる「秘密」と「魅力」を、たっぷりご紹介します! その昔、天下を取ったShogunが活躍した名古屋。「名古屋城」や「ジブリパーク」が有名ですが、実は和食を象徴する”UMAMI”を生み出す食文化の宝庫なんです。 ■What’s HAKKO? 和食の味を左右する「調味料」や世界中で人気の「日本酒」づくりにおいて「HAKKO技術」は、重要な鍵を握る存在です。 ■What's Nagoya like? 日本の中部地区に位置し、空路・陸路共に、ハブとなる名古屋。 恵まれた自然環境と風土によって、独特の発酵食文化を育んできました。伊勢湾と三河湾に囲まれた知多半島は、風光明媚な地で、古くから酒や酢・味噌・たまりなどの醸造業が盛んです。徳川家康の生誕地である西三河は「八丁味噌」や「白醤油」といったユニークな発酵調味料の歴史を紡いでいます。