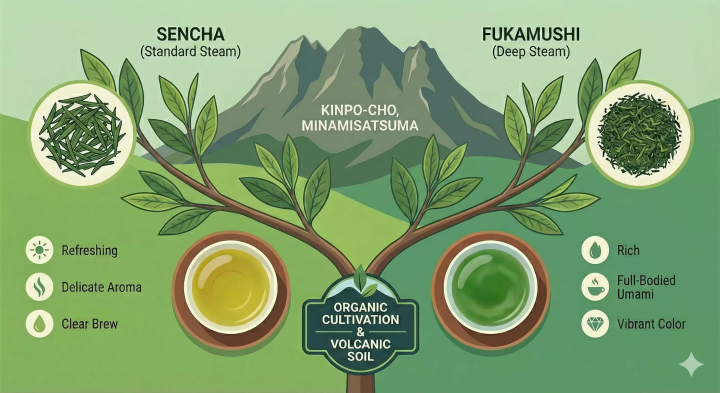お酒好き必見!京都から日帰りで滋賀県の酒造を巡るおすすめモデルコース

滋賀県草津市には「太田酒造」と「古川酒造」という老舗の酒蔵が2軒あります。絶品な日本酒を楽しみながら、草津市を散策してみましょう!
約3時間
京都から電車で20分で行ける滋賀県草津市とは
京都から近く便利で注目を集めている滋賀県「草津市」。宿泊施設や飲食店も充実しており、混雑から少し足をのばしてのんびり過ごすのにおすすめです。電車(JR琵琶湖線)で京都から約20分。大阪駅からは約50分。高速道路も通っていて、車でのアクセスも便利です。
かつては道しるべとして使われていたのが、道標です。「矢倉道標」は現在の瓢泉堂軒先に残っています。享保15(1730) 年に高さ5尺 (約 1.5m) のものが建てられましたが、旅人に見えにくいということで、 寛政10 (1798) 年2月に、 矢橋浦船持惣代船年寄・長七、 同断・茂平次らが、膳所藩主に 「大きな道標に建て替えたい」 と許可願いを出て、高さ6尺6寸(約2.0m)のものに建て替えられました。


東海道草津宿で、宿場と共に育った古川酒造。日本酒銘柄「東海道草津宿 天井川」は化学農薬や化学肥料を使わずに育てた草津市産のお米を使用して造られています。酸味が効いたなかにほのかな甘みが感じられる濃のう醇じゅんで旨口な味わい。草津市以外の地域からもファンが訪れます。
大名も旅人も道中安全を祈願したと云われる1200余年の歴史を有する、滋賀県隋一の古社です。東海道に面して鎮座し、古くより厄除開運・交通安全の神社として信仰を集めています。 初詣、節分大祭や五月の例大祭、七五三参りには多くの参拝客で賑わいます。春には桜が咲き、桜の名所としても人気です。


太田道灌を先祖に持ち、草津宿に酒蔵を構える太田酒造。「純米吟醸 草津政所」は、滋賀県産のお米「秋の詩」を使って作られた日本酒で、フルーティな味わいが特徴です。もうひとつの「単式蒸留焼酎大吟醸粕取焼酎草津政所」は、草津市産の「山田錦」を使って作られた大吟醸の酒粕の焼酎。こちらの焼酎は令和4年に新たに草津ブランドに認定されています。

趣きある外観は、まるで江戸時代にタイムスリップしたかのよう。
東海道と中山道の分岐点を示す「追分道標」です。
滋賀県草津市の「酒造めぐり」の旅は楽しめましたか。今回のモデルコースで紹介したスポット以外にも、草津駅周辺には、草津宿本陣、琵琶湖、グルメなど見どころが沢山あります。また、観光とあわせて宿泊施設でゆっくり滞在してみてください。
このモデルコースで紹介したスポット
滋賀県草津市の観光旅行情報を紹介しています。自然いっぱいの水生植物公園みずの森や琵琶湖博物館、歴史を感じる立木神社や三大神社、草津宿本陣、家族で楽しめるロクハ公園など魅力的なスポット・ホテル・グルメ情報が満載。