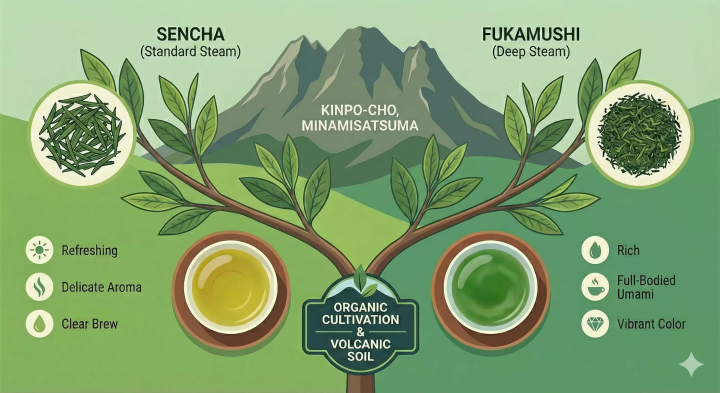【日本の文化】明けましておめでとうございます!日本のお正月の過ごし方をご紹介!

年間を通して、様々な伝統行事を行う日本ですが、中でも正月は特別。正月を迎えてから終わるまで約1か月にわたって多くの行事があります。失われつつある習慣もありますが、日本に住む人がどのように正月を祝ってきたのかをご紹介します!
Gold-Guideは株式会社JR西日本コミュニケーションズが運営するガイドマッチングプラットフォームで、訪日旅行者と優秀な通訳ガイドをマッチングさせて、ガイドツアーを提供しています。
日本で一番大きなイベントはお正月(1月)

お正月は、準備から片付け、お食事やご挨拶など、古くから守られている伝統的な行事が数多く存在しています。元来、正月は1月全体を指すものですが、現在では正月=正月休みを指して使われることが多いです。正月休みは、一般的に12月29日から1月3日ごろまでの間を指し、この期間は特に企業はお休みとなることが多いです。なんと、今年はカレンダーの並びが良く、9連休という長期休暇を実現した企業が多く話題となりました。一方で、昔は正月に併せてスーパーなど飲食店も休業をしているところが多くありましたが、個人商店以外の大型店舗では1月1日だけを休業とするところも増えています。
-
目次
- 正月事始め
- 正月事始めは何をする?
- ちょこっと豆知識!
- お正月飾り
- 新年を迎える前にちょっと待った!!!大晦日にやることは?
- 除夜の鐘
- 除夜の鐘がつけるお寺はどこ?
- 三が日にしてはいけないこと
- 三が日が終わっても行事は続きます!1月7日
- 十日戎 1月10日
- 成人の集い 1月の第二月曜日
- どんど焼き 1月14日~15日
- 正月に旅行する際に気を付けること
正月事始め
正月事始めとは正月を迎える準備を行うことです。地域によってばらつきはありますが、一般的には12月13日から始め、12月28日までに終わらせるとよいとされています。日本では昔から正月になると「年神様」が山から降りてきて、各家庭に幸せをもたらすと言われており、年神様にたくさんの幸せを授けてもらうために、さまざまな正月行事や風習が生まれたそうです。正月の準備することは、年神様をもてなす為の準備といえます。

正月事始めは何をする?

①すす払い→1年間でたまった家の汚れを払い清めます。つまりお部屋の掃除をすることです。「きれいにすればするほど、年神様から授けてもらえる幸運が多くなる」とされています。すす払いは、実際にたまった家の汚れを落とすだけでなく、「厄を落とす」という意味も込められています。
②松迎え→正月の準備に必要な木を集めに山へ行くことを指す言葉です。昔は、年男が正月事始めに恵方の山へと出向き、正月飾りである、門松を作るための松や料理に使う薪などを採ってくる風習がありました。現在はなくなりつつある風習です。
③正月飾り→12月13日の正月事始めから飾り始めるのが、古くからの習わしですが、近年は25日までクリスマスの飾り付けをしている家庭が多く、26日以降に正月飾りを準備するケースが増えています。実に日本らしいですね(笑)
*正月飾りについては下の章でご紹介しますね。
ちょこっと豆知識!
お正月になるとよく耳にする、4つの言葉「大晦日」「元日」「元旦」「三が日」は一体何を表しているのでしょう?
実は、大晦日は12月31日を、元日は1月1日を、元旦は1月1日の日の出(朝)を、三が日(正式には正月三が日)は1月1日から3日までのことを指します。晦日とは月の最後の日のことを指し、1年の最終日ということで大晦日と呼ばれるようになりました。また、元(GAN)は日本語で一番初めという意味を持ち、日は(JITSU)は日を指しますので、元日は年の始まりの日1月1日ということです。元旦の旦(TAN)は日本語で朝の意味を持ちます。
またあまりなじみのない言葉ではあるのですが、上記以外に「松の内」という言葉もあります。松の内とは年神様がいる期間のことです。一般的には1月7日までを指します。(地域によっては1月10日、15日の場合もあります)
このように正月だけに仕様されるような言葉も数多く存在しています。
お正月飾り

お正月飾りは、新年に幸運をもたらすとされる年神様(歳神様)を迎え入れ、その加護を受けるために飾られるもので、日本の伝統文化に深く根ざしています。では、いくつかご紹介しましょう。
①しめ飾り→年神様をお迎えするために玄関などに飾られる、お正月のとても大切な飾りです。年神様が降臨する場所を清める意味を持つ重要な飾りであるため玄関に飾られることが多く、しめ飾りを飾ることで邪気を払い、その家が神聖な場所で神様を迎える準備が整っていることを示します。
②輪飾り→しめ飾りの一種で、家族の団結や繁栄を象徴する円形(輪の形)の飾りです。通常、玄関や水回り、個人の部屋などに飾られ、家の中の清浄な空間を守る役割を果たします。この飾りは、円形(輪の形)であることから、終わりがなく永続的と考えられ、無限の繁栄と家族の団結を象徴しています。飾る場所としては、家全体に良い運気が巡るという意味で家の中心に近い場所や、また、生活の場を清めるという意味で水回りに設置するのが良いとされています。
③門松→日本の伝統的なお正月飾りの代表格であり、家の門や玄関先に飾られることが一般的です。松と竹を組み合わせた門松は、年神様が迷わず家に訪れるための目印として、古くから日本の家庭で親しまれています。松は、寒い冬でも緑を保つことから、青々とした生命力の象徴であり、竹は、成長が早く、真っ直ぐに伸びることから清廉潔白と繁栄を意味します。門松の三本の竹は、天・地・人を表しており、これらが調和することで家族の平和と繁栄を祈る意味も込められています。また、門松は一般的に左右一対で対称に飾られることが多く、玄関の両脇に置くことで年神様を迎える準備が整うとされています。
④しめ縄→神聖な空間を区切り、悪霊や邪気が入らないようにするための結界としての役割があり、玄関や神棚に飾られるのが一般的です。しめ縄を飾ることで、年神様が安心して降臨できる環境を整えます。
⑤鏡餅→丸く平たく作り、大小二つを重ねた餅で、年神様への供物であり、その年神様が宿る依り代として大切にされています。二段重ねの餅は、過去と未来、陰と陽などの二元性を表し、また、「福が重なる」「円満に年を重ねる」という意味を持つことから、家庭の円満や繁栄を願うものと考えられています。鏡餅の上に乗っている橙(だいだい)には、「家系が代々繁栄するように」という願いが込められています。この鏡餅を飾り棚からおろして食べる行事を鏡開きといいます。
⑥干支の置物→その年の干支にちなんだ動物の形をした縁起物で、新しい年を迎えるにあたって、幸運を呼び込む役割を持っています。干支は、12年ごとに巡るもので、その年の象徴とされる動物が置物として用いられます。
⑦破魔矢→邪気を払う力があるとされる神聖な矢で、お正月に神社で授与されます。神棚やリビングの高い位置に飾るのが一般的で、家の中に飾ることで悪運を退け、家内安全を願うものです。もともと、破魔矢は、武士が戦勝祈願や厄払いのために使用していたものが由来とされています。射られた者を退ける力があると信じられており、家の中で災いが起こらないようにとの願いが込められていました。
新年を迎える前にちょっと待った!!!大晦日にやることは?
新年を迎える前日12月31日にやることといえば「年越しそばを食べること」です。この年越しそばを食べるようになったのは、江戸時代の頃だといわれています。もともとは細くて長いそばにあやかり商売が長く続くようにと商人を中心に食べられていたそうですが、転じて大晦日にこれからの長寿や延命を祈願して長いそばが食べられるようになったといわれています。また、ほかの麺と比べても細長く切れやすいことから、その年の厄を祓うという意味で食べられるようになったという説もあります。このほか、年の湯と呼ばれる年内最後の湯に浸かったり、掃き収めと呼ばれる簡単な掃除をしたりします。

除夜の鐘
除夜の鐘は、大晦日にお寺でつく鐘の音ですが、大晦日の夜から明け方まで日付をまたいで行われます。除夜の鐘は煩悩の数と同じ108回鳴らされるのが有名な話で、仏教の教えに従って煩悩を祓うために108回鳴らされるという説や、日本の言葉でとても辛いことを表す四苦八苦を数式にあてはめ4×9、8×9を足した108にしているともいわれます。また季節の目安である二十四節季と七十二候にちなんでそれぞれの月と数を足して108にしたという説も、、なかなか奥が深いですね、、、。

除夜の鐘がつけるお寺はどこ?
除夜の鐘つきを一般の参拝者が体験できるお寺があります。関西で有名なのは①四天王寺②太融寺③東大寺。参加できる人数には限りがあり、整理券配布等を行っているお寺もありますので、ご注意!事前に調べていきましょう。

〇初日の出を見る→1月1日に行う最初の行事は、初日の出を拝むことです。初日の出は新年最初の日の出のことで、明治以降に縁起がいいと広まったことから拝むようになったとされています。
〇正月料理を食べる
①おせち・・・おせちは節句を意味する「お節供」に由来しており、お節供は神様へのお供え物を指します。中国・唐で特別な日を節と呼んでおり、日本でも季節の変わり目に祝い事を行う日を節日と呼ぶようになりました。お節供は節日に神様に供えるもので、おせちはお節供を略したものとされています。おせちには縁起のいい料理を詰め合わせるのが基本です。
②雑煮・・・正月にお雑煮を食べるようになったのは平安時代からとされており、餅の入ったお雑煮は特別な日に食べるものとして扱われていました。お雑煮の語源は煮混ぜといい、さまざまな食材を煮て作ることに由来しています。
③お屠蘇・・・お屠蘇は数種類の生薬を酒とみりんに浸けて作る薬草酒です。邪気払いと長寿祈願という意味が込められており、正月に飲む祝い酒として知られています。お屠蘇が中国から日本に伝わったのは平安時代のことですが、庶民が正月に飲むようになったのは江戸時代からとされています。
〇初詣に行く→初詣は年が明けてから初めて神社やお寺をお参りすることで、新年の幸せを祈願するためのものです。三が日に行うのが基本ですが、松の内の間にお参りすればよいとされています。
〇初夢→初夢は新年に初めて見る夢を指します。厳密には年が明けてから最初に寝た日の夜とされており、1月1日から1月2日にかけて見るという説が一般的です。とはいえ、1月1日に就寝せず1月2日に寝た場合は、2日から3日かけて見た夢を初夢としても構いません。あるいは、年が明けて最初に寝たときに夢を見なかった場合は、日付にかかわらずその年に初めて見た夢を初夢とするという考え方もあります。
〇書初め→1月2日に行うことが多い書き初めは、新年を迎えてから初めて文字を書いたり絵を描いたりすることです。新年の抱負や祈願を盛り込み、努力や目標、健康などの意味をもつ四字熟語を書くのが一般的です。
〇お年玉をあげる、もらう→本来は年神様から年魂(としだま)という新しい魂を授かることを指していました。神様が宿った鏡餅を「御年魂/御年玉」として家族で分け合い、1年を無事に過ごせるようにという願いを込めて食べていたとされます。現在では親族からもらうお金を指しています。お年玉はポチ袋に入れられていることが多いです。
三が日にしてはいけないこと
三が日はやることがたくさんあるのですが、実はこの間にしてはいけないといわれていることがあります。代表的なものは①掃除②刃物を使うこと③火を使う煮炊き④四つ足歩行の動物の肉を食べること⑤喧嘩⑥賽銭以外のお金を使うこと。皆さん気を付けてくださいね!!
三が日が終わっても行事は続きます!1月7日

1月7日には七草粥を食べます。七草粥とは五節句の一つである人日(じんじつ)に食べる行事食です。七草粥は無病息災や長寿健康という願いが込められており、「春の七草」と呼ばれる7種類の食材を使って作ります。
十日戎 1月10日

漁業の神、商売繁盛の神、五穀豊穣の神として有名な「七福神」の戎(恵比寿)様を祀るお祭りです。本殿で祈祷をしてもらう会社も多く、大阪駅周辺の寺社はこの時期ご祈祷の予約で混みあっています。戎様を祭っている神社は特に関西圏に多く、西日本を中心に人気のあるお祭りです。
成人の集い 1月の第二月曜日

2022年より、成人式と呼ばれていたものが成人の集いと名称が変わりました。これまで20歳になると成人とされていたのですが、年齢の引き下げにより18歳より成人とすることに決まったためです。日本では18歳から成人の仲間入りですが、これまで同様にお酒やたばこは20歳を超えてからとなっています!この日は豪華な着物を着て式に参列する方が多いので、街で見かけたらおめでとうと声をかけてあげてください。
どんど焼き 1月14日~15日

正月飾りなどを火で焼き、その火で焼いたお餅を食べる行事です。その餅を食べると無病息災になるといわれています。
正月に旅行する際に気を付けること
①銀行の休業→12月31日から1月3日までは休業をする銀行が増えます。(銀行によってはもっと長いこともあります)キャッシュレス決済が進んでいるため困ることは多くないと思いますが、注意が必要です。
②飲食店の休業→銀行と同じく12月31日から1月3日までは休業する店舗が増えます。一方で百貨店や大型の店舗などは1月1日のみを休業とし、お正月休み期間は営業時間を変更するなどして対応しているところが増えます。お正月メニューのみの取り扱いとなり、通常メニューが頼めないところもあったりします!また個人経営のお店などは休業していることが多いのでご注意。
③観光施設→寺社仏閣は正月のイベントなどを行うため、年末年始でも空いていることが多いですが、それ以外の観光施設は12月31日、1月1日は休業としていることが多いです。お城は年末から年始にかけて休業となっているところが多いです。行く場所が決まっている場合は、必ずホームページ等で営業時間を確認しましょう。
地域によっても内容が変わるので、その違いを楽しむのも面白いですよ!
【Gold-Guide】は訪日観光客と優秀な通訳ガイドをマッチングさせガイドツアーを提供するプラットフォームです。 日本での特別体験をお求めのお客様に思い出に残るガイドツアーを提供します。 日本の魅力を世界中の皆様へ