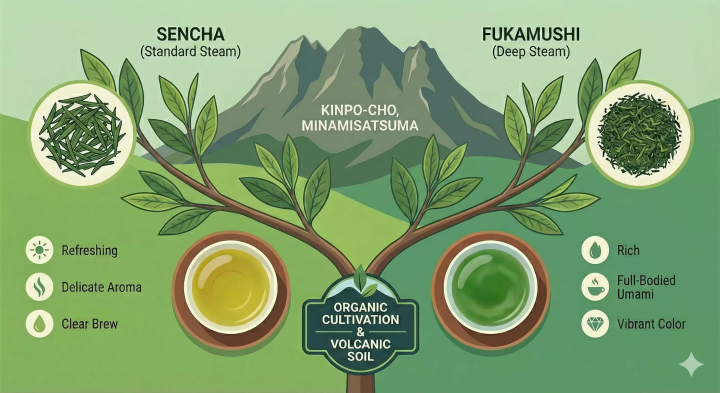日本のことば事典「熱燗」

同じ銘柄でも温めて飲んだり冷やして飲んだり、様々に楽しめることが日本酒の魅力のひとつ。温めて飲む「熱燗」の中にも実はさまざまな飲み方があることを知っていますか?今回は熱燗のバリエーションと、おいしい作り方をご紹介します。

「熱燗(あつかん)」とは、日本酒の飲み方のひとつ。大変親しまれている飲み方で、居酒屋で日本酒を頼むと「熱燗」にするか、もしくは「冷(ひや)」にするかと、多くの場合尋ねられます。今回は、寒くなった季節により美味しく感じられる、日本酒の「熱燗」をご紹介いたします。
「熱燗」という飲み方

日本酒を徳利(とっくり)という陶器の器に注ぎ、その徳利を外から加熱した飲み方です。
お酒自体に加熱する行為のことを「燗(かん)をつける」もしくは「お燗(おかん)」するといいます。
一般的にはお酒には日本酒を使いますが、まれに焼酎なども「熱燗」で飲まれることがあります。徳利も熱くなるので陶器でできたものを使います。グラスはお猪口(おちょこ)という、こちらも陶器でできたものに注いでいただきます。基本的には、温める際にお水、お湯などで薄めることはしません。
「熱燗」の始まり

お酒を「熱燗」にして飲む風習は日本では意外と古く縄文時代までさかのぼります。
尖った土器を使用しお酒を入れ、熱い灰に突き刺し温めたとされています。庶民に「熱燗」が浸透したのは江戸時代に書かれた人気作家の本に書かれたことから、広まったとされています。
「お燗」の温度で呼び方が違う?
お酒は「お燗」の温度によって呼び名が変わります。
味や香りも違ってきますので、いろいろ試してみてはいかがでしょうか。
①日向燗(ひなたかん)
温度は30度であまり温度の高さは感じない程度。ほんのり日本酒の香りが引き立ちます。
②人肌燗(ひとはだかん)
温度は35度でさわると温かく感じる程度。米や麹の良い香りが出てきます。
③ぬる燗(ぬるかん)
温度は40度で熱くはない程度。香りがよく出てきます。
④上燗(じょうかん)
温度は45度で注いだ時に湯気が出る程度。引き締まった香りを感じるようになります。
⑤熱燗(あつかん)
温度は50度で徳利からでる湯気が熱く感じる程度。香りがシャープになりキレの良い辛口になります。
⑥飛びきり燗(とびきりかん)
温度は55度で徳利をもつと熱いくらいです。シャープな香りで味覚もより辛口に感じます。
おいしい熱燗の作り方
自宅でも簡単にできる「熱燗」。時間はかかりますが、まろやかな香りの日本酒が楽しめる熱燗の作り方です。一番風味を壊さず、香り良くお燗できますので是非作ってみてください。
1.お酒を徳利の9分目まで注ぎます。この際徳利の口にラップをするとお酒のよい香りの成分が飛びません。
2.鍋を用意し、水を入れます。先ほどの徳利を入れてみて徳利の半分が浸かるようにお水の量を調整します。
3.徳利を必ず取り出してから、お鍋を火にかけお水を沸騰させます。沸騰したら、火を止めてください。
4.火を止めた鍋に徳利を入れてください。大体2~3分温めます。
5.お酒が徳利の口まで上がってきたら「熱燗」の完成です。
時間をかけないですぐ「熱燗」が飲みたい、という方には電子レンジでも温められます。徳利にラップをかけ40秒ほどで「熱燗」になります。ですが電子レンジは温度にムラが出来てしまうので、20秒で一度取り出し徳利を振って温度を均一にしてください。その後再度過熱をし、自分好みの温度に調整すると良いと思います。
「熱燗」は人によっては、真夏のとても暑い時期でも好んで飲まれる飲み方ですが、これから冬にかけて「熱燗」が最もおいしく飲める季節がやってきます。日本酒を飲む際にはぜひ「熱燗」にも挑戦してみてくださいね。
日本への訪日外国人の方が、もっと増えますように!