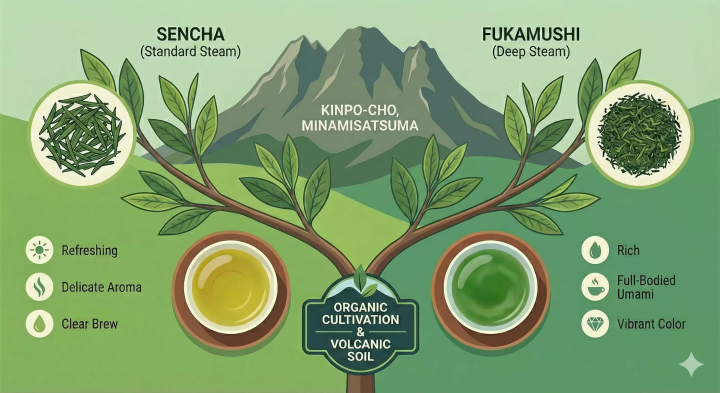飛騨高山の夏を満喫!勇壮な手筒花火を見に行こう

日本の真ん中、岐阜県。その北部にある飛騨高山の夏の風物詩、「手筒花火」(てづつはなび)をご紹介します。勇壮な男たちが火薬の入った筒を手で持ち、火の粉を全身に浴びながら巨大な火柱を打ち上げます。最後は筒の底から爆音と共に火花が飛び散り、大変迫力ある花火です。日本中で、愛知県豊橋市とここ飛騨高山でしか見ることができません。
本サービスにはプロモーションが含まれています
-
目次
- 飛騨高山手筒花火(ひだたかやまてづつはなび)の歴史
- 盛大な炎が厄を祓う
- 木遣り唄(きやりうた)と獅子舞(ししまい)
- 激しく燃え上がる火柱と腹に響く轟音
- 飛騨高山手筒花火の詳細
- 同時期に行われるイベント
- 飛騨高山へのアクセス
- 飛騨高山をもっと知るには
飛騨高山手筒花火(ひだたかやまてづつはなび)の歴史

飛騨高山の手筒花火は約40年前に始まりました。はじめは規模も小さく数人から始まりましたが、手筒花火の勇壮さに惚れ込んだ人が次々と加わり、今では40人以上のメンバーと180本もの花火の規模となり、飛騨高山の夏を代表する行事となりました。

筒は大小あり、火薬を仕込むと8kgもの重さになります。点火すると火柱が8~10mもの火柱が大きく上がり、筒を抱える肩や腕に熱い火の粉が降り注ぎます。
参加者は独特の美学を持って花火に挑みます。筒を垂直に抱え、火柱がまっすぐに上がり、火の粉が傘のようなシルエットを描くのが美しいのだ、と彼らは誇らしげに語ります。
盛大な炎が厄を祓う

日本古来の考え方に「厄払い」(やくばらい)というものがあります。自分では制御できない意志の力で定められている悪い運命のことを「厄」(やく)と呼び、「厄」を自分から遠ざける行為のことを「厄払い」と言います。
様々な方法があるとされていますが、その一つに炎が悪い運命を浄化するという考え方があります。手筒花火は参加者だけではなく、花火を見る観覧者の厄を祓い、人々の幸せを願う行事です。

花火を始める前に、神社で祈りを捧げます。花火は美しく華々しい行事ですが、一方で火事や事故の危険性もはらんでいます。自らと仲間たち、観覧者のすべてに危険がふりかからぬよう、祈りを捧げ、神主が厄を遠ざける儀式を行います。
木遣り唄(きやりうた)と獅子舞(ししまい)

儀式の後、神社から花火の会場まで歌を歌いながら行列になって進みます。この歌は「木遣り唄」(きやりうた)と呼ばれ、古くから日本の各地で歌い継がれているものです。元来は、重い物を運ぶ際にお互いのタイミングを合わせる為に歌われていた労働歌でした。
古来より木造建築の多い日本では火事が多く、江戸(300年前の東京)では身のこなしの軽い大工が火消しに携わるのが習いでした。江戸の町を救う火消しの男たちは大変尊敬されており、人々は結婚式や祭礼に彼らを招き、木遣り唄を歌ってもらうことを喜びとしたのです。
飛騨高山の木遣り唄は江戸火消しの木遣り唄を基に、飛騨高山らしさを歌詞に加えて工夫したものです。この歌を歌いながら大通りを歩いて行くと、歌う者も聞くものも気持ちが高揚し、これから始まる花火への期待が高まります。

花火の前のひととき、獅子舞が奉納されます。獅子舞も同じく悪鬼を遠ざけるものです。夕闇が濃くなる中激しく舞う獅子舞は、この世のものでないような神秘的な風景です。
激しく燃え上がる火柱と腹に響く轟音






飛騨高山の中心を流れる宮川(みやがわ)の河川敷を舞台に行われる「飛騨高山手筒花火」。1時間もの間に180本もの手筒花火に次々と点火され、観覧する人々は熱狂します。
豪快さと裏腹に、消えゆく花火の儚さが北国の短い夏を象徴するような、飛騨高山の手筒花火。あなたもぜひ飛騨高山を訪れ、この勇猛な行事をその目でご覧になってください。
飛騨高山手筒花火の詳細
日時:2024年8月9日(金)
時間:19:30~20:30
場所:宮前橋(みやまえばし)付近
同時期に行われるイベント
飛騨高山へのアクセス
飛騨高山をもっと知るには
飛騨山脈(北アルプス)に代表される雄大な自然に囲まれ、江戸時代の面影を残す古い町並や、春と秋の高山祭など、歴史と伝統文化が息づく町「飛騨高山」。飛騨高山温泉や奥飛騨温泉郷などの温泉と、飛騨牛や日本酒などのグルメも充実しています。 特に春と秋に行われる高山祭は絢爛豪華な屋台(山車)を中心に、精巧な動きをみせるからくり人形や絵巻物の再現のような祭行列が特徴で、国内外より多くの方々が見物に訪れます。 東京からは約6時間、大阪からは約4時間の道のりです。周囲には白川郷や上高地、金沢など日本有数の観光地があり、飛騨高山を中心として様々な土地へ訪れることができます。 欧米型のホテルや伝統的な旅館、家庭的な民宿や長期滞在に向いたホステルなど、さまざまなタイプの宿泊施設が混在しており、利用者の需要に応えられるキャパシティがあります。 自然・歴史・伝統・文化・美食、様々な分野に携わる飛騨の人々は素朴で温かく、訪れる人々を心からもてなします。