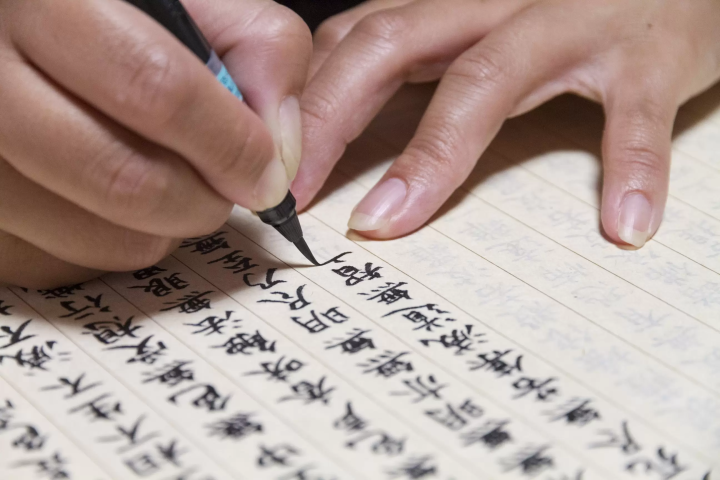能楽をもっと身近に! 能楽師のトークショーと市民狂言会鑑賞

能や狂言に対して「敷居が高くて難しそう」と感じる方は多いのはないでしょうか?今回は、能楽師とのトークショーを通じ、能楽を身近に感じてもらうことを目的に開催されたイベントに参加しました。その模様をご紹介します。
この日登壇したのは2人の能楽師、狂言方大蔵流の14世茂⼭千五郎さんと、ワキ方高安流の有松遼⼀さん。トークショーは、ゆどうふで有名な「南禅寺順正」の⾖腐料理を味わう中で行われ、その後、京都観世会館にて茂⼭さんが出演する「市⺠狂⾔会」を鑑賞しました。
お⾖腐のように、⽇常で楽しめる狂⾔を⽬指して

最初に登壇されたのは、⼗四世茂⼭千五郎さん。この⽇の司会は⼀般社団法⼈Discover Nohin Kyoto代表理事でアメリカ出⾝のジュリア・ヤマネさん(写真右)で、⾃⾝も能楽師に師事されるほどの能楽ファン。現在は能楽の海外への普及にも⼒を⼊れているそうです。
冒頭、茂⼭さんは「能楽を分かりやすく⾔うと、能と狂⾔がワンセット、能はシリアスな⾳楽劇。狂⾔はコミカルなセリフ劇で、全く正反対の演劇を楽しめる」と説明しました。江⼾時代初期から続く能楽師の家庭に⽣まれ、初舞台は3歳の頃。司会のジュリアさんからの「⼦どもの頃から特殊な家系だと感じていましたか?」との質問に対しては、「物⼼が付く前から稽古をして舞台に⽴っていたので、それが当たり前だった」との回答。また、曽祖⽗、祖⽗、⽗はすべて狂⾔師であり、家庭では舞台の話が中⼼。そのため、ついていけないと「居場所がない」とも感じることも。そんな環境の中で「あなたが継ぐよ」と⾔われて育ち、辞めたいと思ったことはなかったと語りました。

(写真:この⽇出されたお料理)
初心者はまず、舞台の空気感を楽しんで
能楽には約200の曲があり、祇園祭や清⽔寺、禅にまつわる話など、京都に関連した内容が多いのが特徴です。そのため、京都で暮らしているとその内容がより⾝近に感じられるのだそうです。
能楽は「敷居が⾼い」と思われがちですが、茂⼭さんからは「実は、僕たちも台詞の全ては分かりません(笑)。まずは空気感を楽しんで下さい」とアドバイスしました。内容を理解しようとするよりも、お囃⼦の⾳⾊や⾐装の美しさなど、感じる気持ちが⼤切なのだそうです。それは⽇本⼈が海外のオペラを観て、台詞が分からなくても⾳楽や⾐装、演出に感動するのと似ています。
悪口を逆手に捉えた「お豆腐狂言」
茂⼭家の家訓は「お⾖腐狂⾔」。それは今から4代前の⼗世茂⼭正重(⼆世千作)の話に由来します。江⼾時代、能楽は武家社会に⽀えられえていましたが、⼤政奉還でそれが無くなり、能楽師は⽣活が苦しくなります。それでも、武⼠や公家など特別階級のためのものだった能楽は、能舞台以外で上演ができない厳しいしきたりがありました。しかし、正重はそれを気にせず、さまざまな場所で狂⾔を上演したところ、その様⼦を⾒た周りの⼈々から「茂⼭家はまるでお⾖腐のようだ」と悪⼝を⾔われます。京都では⾖腐というと、ごく⽇常にある⾷材。「とりあえず⾖腐を買えばその⽇のおかずは何とかなる」という感覚で茂⼭家の狂⾔を指したのですが、正重はそれを逆⼿に取ります。「別に⾖腐でもいいじゃないか、広く京都の町の⼈に愛される狂⾔を⽬指そう」 という覚悟となり、今⽇まで続く家訓となりました。
この話を受けて、ジュリアさんは「現在京都の狂⾔師は15、6名ほどおり、能や楽器をされている⽅を合わせると100名ほどの先⽣がいるそうです。ですが、まだまだ敷居が⾼いと思われています。是⾮お⾖腐のように気軽に鑑賞して下さい」と締め括りました。その後、出席者から海外の⽅向けの公演で盛り上がるところについて質問がありました。茂⼭さんによると、⾝振り⼿振りが多い曲と、お酒に対する失敗の話は万国共通で盛り上がるとのことでした。

(写真:順正名物のゆどうふ。「⾖腐は⾝近な⾷材だが、味付けにより⾼級な味にも、庶⺠の味にもなる」と正重は⾔いました)
能楽には、日本文化のエッセンスが詰まっている
シテ方続いて登壇したのはワキ方の有松遼⼀さん。能楽師というのは「シテ⽅」「ワキ⽅」「囃⼦⽅」「狂言方」という4つの、会社の部署のようなものがあり、有松さんは「ワキ⽅」に属しています。ワキ⽅は1番最初に舞台に登場し、時代や季節、これから何が起こるかという舞台設定をして、観客を物語の世界に導きます。その後、主役であるシテ⽅が舞台中央で演じますが、その間ワキ⽅は、観客に近い舞台の右⼿前でずっと座っています。それは、物語を設定するワキ⽅が観客の代表のような⽴場で、シテ⽅を⾒守っているような、不思議な役だと説明しました。

有松さんは代々狂⾔師の家系に⽣まれ育った茂⼭さんとは違い、出⾝は東京のサラリーマン家庭。京都の⼤学に⼊学して能楽と出会い、⼤学院⽣になった時に師匠に⼊⾨しました。「20歳になるまで能楽は⾒たことがなかった」と語る有松さんが能に惹かれた理由は「独特の分からなさ」で、それを知りたいと思ったからでした。
ジュリアさんもまた、「私も25年以上能の稽古をしていてもまだまだ分からない、知りたいことがたくさんあるので続けたくなる」と話しました。
平安時代から続いている、日本文化のエッセンスを浴びる
能楽が⼤成したのは今から600〜700年前の室町時代。応仁の乱などの戦争や天災などで荒廃した都では、平安時代の和歌を中⼼とする美しい王朝⽂化を懐かしみ、観阿弥・世阿弥がそのエッセンスを能楽に取り⼊れて表現しました。そのエッセンスは、同じく室町時代に確⽴された茶道や花道や書道、禅などの今で⾔う「ザ・⽇本⽂化」にも繋がっています。つまり能楽を鑑賞することは、⽇本⽂化の根源に触れることなのです。

1日1公演の豊かさ、芸能でもあり神事でもあるような謎を楽しむ
「能楽は数⽇間かけて収益を得る公演と違い、1⽇1公演しかありません。そのために、皆がその1⽇に全⼒を尽くすという豊かさがある」と、有松さん。ジュリアさんからも「能楽のルーツが宗教儀式や祈祷なので、チケットを販売しているとはいえ、観客のためだけに演じていない感覚があるのでは」と付け加えました。また、舞台の背景に松が描かれた鏡板があリますが、理由は松の⽊は神様の拠り所とされているからだそうです。今でも神社では、神様の⽅向を正⾯にし、観客は演者の背中を観るという舞台があり、これは歌舞伎や⽇本舞踊にも通じていて、⽇本⽂化の根源を⾒ることができます。⽂筆業も⾏う有松さんは、シテ⽅として脇座に座っていると、頭が整理され、次々に書きたいことが浮かんでくるのだそうです。「能楽は芝居であるが神事のような側⾯がある。謎が多いが、謎がなくなったら⾯⽩くない。神社やお寺でお参りした時に何故⼼が落ち着くのか説明できないのと同じ感覚だ」と話しました。
司会のジュリアさんも能のことを「⽇本⽂化の溶け残った雪のよう」と例えました。結晶化されたものが残っているけれど、それが何のためにあるのか理解できないところが魅力なのだと、締めくくりました。
物事に理由や効率、数字が求められることが多い現在社会では、「ただ感じる」ことが難しくなっています。美しく、そして分からなさも楽しめる能楽の舞台を観ることで、⼼の豊かさが得られるのではないでしょうか。
市民狂言会では、アプリを使って英語の解説が楽しめる工夫も

トークショーの後は、能楽堂「観世会館」で「第277回 市⺠狂⾔会」を鑑賞しました。市⺠狂⾔会は⼤蔵流茂⼭千五郎家・忠三郎家の協⼒により1957年から開催している、気軽に狂⾔を楽しめる会です。各演⽬の初めに解説があるので、初⼼者には心強いです。

この⽇の演⽬は、初めに⾒どころの説明があり、狂⾔の「今参り」、狂⾔⼩舞の「⾙尽し」「福の神」が続き、最後に狂⾔「狐塚」という内容でした。

さらに今回は、南禅寺順正でのトークショーの最後に紹介があった、演劇の多⾔語字幕ガイドのアプリ「Gマークアプリ」をダウンロードし、使ってみました。

使ってみると、舞台の内容に合わせて⽇本語と英語での解説を⾒ることができました。
このアプリがあれば、狂⾔初⼼者の⽇本の⽅、⾔葉が分からない海外の⽅に鑑賞のハードルを下げるだけでなく、舞台をより楽しめそうです。
分かろうとせず、ただ感じよう
今回のトークショーでは代々続く狂⾔師の家に⽣まれた茂⼭さんと、⼤⼈になってから能を始めた有松さんという、異なる背景を持つお⼆⼈の話で⼤変興味深いものでした。能を鑑賞するにあたり、2⼈ともに共通していた考えは「分かろうとせず、ただ感じたらいい」いうこと。これは、初⼼者には嬉しいアドバイスだと思いました。
まずはその気持ちを大切にしつつ、そこに補助的な役割で字幕アプリなど新しいテクノロジーが加わると、「ちょっと観てみようかな」という人も増えるのではないでしょうか。
ご希望に応じて、文化体験やガイド付きツアーも手配いたします。気になる方は、ぜひご連絡ください!
場所などの情報
南禅寺順正
住所:京都府京都市左京区南禅寺⾨前
観世会館
京都市左京区岡崎円勝寺町44
市民狂言会について
多⾔語字幕ガイドのアプリ「Gマークアプリ」
私たち”アンバサダー”が、自身の体験や知識をもとに京都の文化観光を多様な言語でご案内します。 神社仏閣庭園、モダン建築、食文化、伝統芸能などの知識と体験、現地での出会いなど最高の思い出を作っていただくために、既存のコースから、オーダーメイドの特別な1日コースまでリクエストにお応えし、京都での忘れられない日々になるようお手伝いをいたします。 ガイドツアーだけでなく、ユニークベニューを活用したイベントから四季折々の京都文化を存分に楽しんでいただける企画まで、スペシャルな体験をご提供いたします。