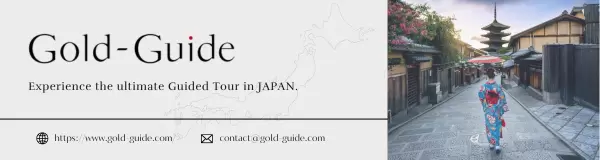【食文化】祝!UNESCOの無形文化遺産登録!!日本の「伝統的な酒造り」

2024年12月5日にUNESC無形文化遺産に日本の伝統的酒造りが登録されました!今回は日本の伝統的な酒造りとGold-Guideおすすめの日本酒ツアーをご紹介します!
Gold-Guideは株式会社JR西日本コミュニケーションズが運営するガイドマッチングプラットフォームで、訪日旅行者と優秀な通訳ガイドをマッチングさせて、ガイドツアーを提供しています。
UNESCO無形文化遺産とは
「無形文化遺産の保護に関する条約」(無形文化遺産保護条約)は,グローバリゼーションの進展や社会の変容などに伴い,無形文化遺産に衰退や消滅などの脅威がもたらされるとの認識から,無形文化遺産の保護を目的として,2003年のユネスコ総会において採択されました。この条約によって,世界遺産条約が対象としてきた有形の文化遺産に加え,無形文化遺産についても国際的保護を推進する枠組みが整い、条約の策定段階から積極的に関わってきた日本は,2004年にこの条約を締結しました。現在23件の登録遺産を保有しています。
登録遺産、伝統的酒造りとは
酒造りは古くから日本に根差してきた食文化の一つで、500年以上前に原型が確立したとされています。伝統的酒造りの技は、「こうじ」の使用という共通の特色を持ちながら、日本各地においてそれぞれの気候風土に応じて発展し、日本酒、焼酎、泡盛、みりんなどの製造に受け継がれ、継承しています。
Gold-Guideの日本酒ツアー
日本で一番広いエリアで楽しまれているのが「日本酒」、九州地域で特に人気のある「焼酎」、沖縄で飲まれる「泡盛」などお酒といっても地域に根差したそれぞれの特色があります。この中で、特に関西を含む西日本を訪れる旅行者が一番出会いやすいのは日本酒でしょう。なぜなら日本の三大酒処は京都(伏見)、兵庫(灘)、広島(西条)とすべて西日本エリアにあるからです。(*諸説あります)Gold-Guideではこの酒処のうち、伏見と兵庫の日本酒ツアーを掲載しています。特に灘は2~3か所の酒造所を巡りしっかりと日本酒について学ぶツアーですので、この機会に日本酒について知りたい方は是非ご予約ください。
明日から使える日本酒の豆知識!これであなたも日本酒ツウ?
①酒蔵とお酒の銘柄はいくつあるの?
現在、全国の酒蔵の数は約1,400。銘柄の数は毎年変動しますが、酒蔵ごとに通常いくつかの銘柄を販売するので、1万ほどにのぼるといわれています。ちなみに日本酒で一番多く使われる感じは「山」です。きれいな水や自然を連想させるからだとか、、
②アルコール度数は?
日本の酒税法で定められている日本酒のアルコール度数は22度未満。販売されている大半の日本酒は、15度前後です。22度以上になるとリキュール扱いでの販売となるのです! ちなみに日本一度数の高い日本酒は新潟県にある老舗・玉川酒造の『越後武士(さむらい)』です。 アルコール度数は実に46度!販売時にはリキュール類として販売されます。
③甘口と辛口
よく日本酒の味を表すときに「甘口」「辛口」といいますが、これは、日本酒を造る過程で生まれる糖がどれだけ含まれるかできまります。「甘口」は発酵が弱く、まだ糖分がたくさん残っているお酒。一方で「辛口」は発酵が進み、糖分が少なくなっているお酒です。日本酒の多糖類のは甘さを感じさせることはほとんどなく、甘い=スイーツのような甘さとはなりません。また感じ方は人それぞれであり、どうやってこの甘口、辛口を見分けるのでしょう?
実はラベルにその答えがあります。日本酒のラベルには、「日本酒度」が「+(プラス)」と「-(マイナス)」で示されています。これは「+」になるほど糖分が少ない辛口で、「-」になるほど糖分が多い甘口という意味です。「どうして糖分が多いのに表示はマイナスなのか」と疑問を感じるかもしれません。日本酒度で示されているのは糖分の量ではなく「お酒の比重」です。お酒の比重を計るには、「日本酒度計」というものを使います。お酒の中に水よりも重い「糖」がたくさん含まれていると、日本酒度計が浮いて「マイナス(甘口)」になり、反対に糖分が少ないと日本酒度計が沈んで「プラス(辛口)」になるのです。
UNESCO無形文化遺産に登録された日本伝統的な酒造りについて是非この機会に学んでみましょう!
Gold-Guideにはお酒分野に強い通訳ガイドが在籍しています!
【Gold-Guide】は訪日観光客と優秀な通訳ガイドをマッチングさせガイドツアーを提供するプラットフォームです。 日本での特別体験をお求めのお客様に思い出に残るガイドツアーを提供します。 日本の魅力を世界中の皆様へ