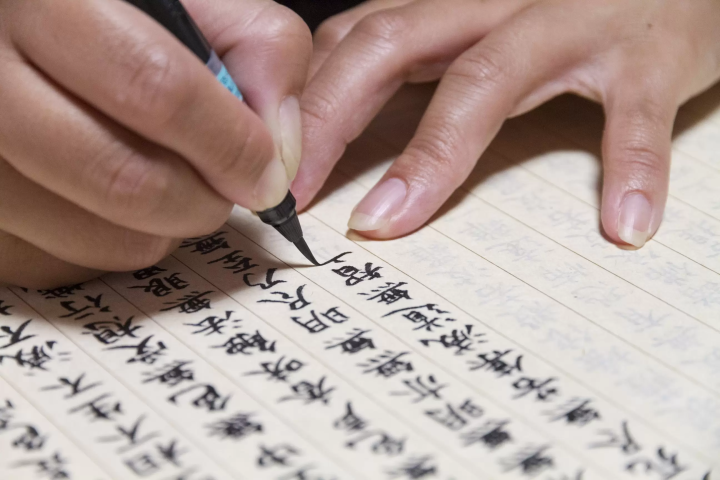灯籠と行燈、提灯の違いは?寺や居酒屋にある照明の種類を解説

ガスや電気が使われるまで、日本では主にロウソクや油の火を照明として利用していました。そのとき使われていたのが、灯籠(とうろう)・行燈(あんどん)・提灯(ちょうちん)などの照明器具です。本記事では、それらの違いを解説します。
「灯籠」「行燈」「提灯」は何が違う?
ガスや電気が使われるまで、日本では主にロウソクや油の火を照明として利用していました。そのとき使われていたのが、灯籠(とうろう)・行燈(あんどん)・提灯(ちょうちん)などの照明器具です。
外国人の方が夜景を見て「あ、日本的だな」と思うのは、現代のネオンサインを別にすれば、これら照明器具の影響であることが多いようです。今回は外国人の方には見分けづらい、日本伝統の照明器具の違いについて紹介します。
灯籠(とうろう)とは

Photo by Pixta
灯籠は主に外で使用された、いまでいう街灯です。灯籠とは「灯り」の「カゴ」という意味で、その名のとおりロウソクの火が風で消えないよう、周囲を囲った道具です。
素材は木や金属などさまざまですか、石で作られたものはとくに石灯籠(灯篭)と呼ばれます。石灯籠はお寺によく設置されているので、観光の際も目にすることが多いでしょう。
行燈(あんどん)とは

Photo by Pixta
室外に設置される灯籠に対し、主に室内で使用されていたのが行燈です。ロウソクや、油に浸した布に火をつけて利用しました。室内で利用しますので軽い木製のものが多く、さらに火の回りは風よけの紙で覆われていました。
枕元に置いておけるほど小さな行燈を、とくに有明行燈と呼びます。
提灯(ちょうちん)とは

行燈と同じように紙で覆われているものの、持ち運びできるよう進化したのが提灯です。やはり軽くて、さらに持ち手がついています。持ち運びが簡単なように、使わないときは折りたたんでおくことができました。
現在では日本風の酒場「居酒屋」の入り口にぶら下げられていることが多いです。そこから日本では居酒屋のことを「赤提灯」と呼ぶことがあります。
現在では少なくなってしまったこれらの照明器具ですが、観光地や日本的な施設に行けばまだまだ見つけることができます。
日本にお越しの際は、ぜひ探してみてください。夜の街歩きに、またひとつ別の楽しみを加えることができるはずです。