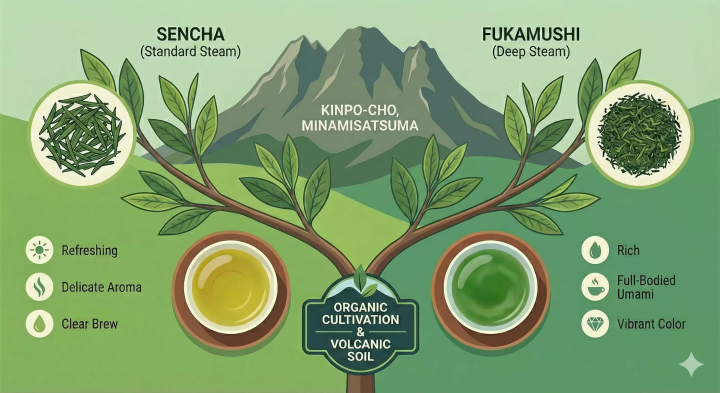三重県松阪市で御朱印巡りをして日本文化に触れる

今回は、三重県松阪市の神社を回る「御朱印巡り」について紹介します。
リフレッシュに!パワーを感じる松阪の御朱印巡りへ
沢山の物や情報に囲まれ、物質的な豊かさに恵まれている現代。
その反面、心の充実を感じたくなる時があります。
そんなとき、御朱印巡りはいかがでしょうか?
今回は、三重県松阪市の神社を、御朱印帳片手に巡ります。

➀松阪神社|見覚えのある御本殿と御神木の穴の秘密

▲松阪神社の入り口
松阪神社の境内へ続く階段を登ると森に囲まれ緑が心地良い空間。

この森は「四五百森(よいほのもり)」。凛とした空気感に気分が晴れます。
松阪神社は35柱の神様を祀る神社です。
元々は「意悲(おい)神社」という神社で、2柱を祀っていましたが、明治41年に、政府の方針により「神社合祀令」が発令され、松阪でも市内各所17の神社がここに合併し、その際33柱が加わり、名前も松阪神社となりました。

▲蔵には、合併前のそれぞれの神社の扁額が納められている。

▲雨竜・八重垣の2つの御神輿
この御神輿は、毎年7月の「松阪祇園まつり」で街に繰り出すもので、ここ松阪神社と、これから訪れる八雲神社、御厨(みくりや)神社の3つの神社から、「3社みこし」として、市中心部の商店街などを練り歩きます。

丸みがあって可愛らしいフォルムの御本殿の屋根。
実は、この御本殿、伊勢神宮外宮の「西宝殿」からそのまま移管したものだそうです。
現在の御本殿は、今から93年前に頂いたもの。木は1,000年でも持つものなので、手入れをして直しながら大事に残しています。
境内を眺めるとどっしりとした存在感の、樹齢900年を越える楠の御神木。

▲御神木は、樹高25m

松阪神社を囲む四五百森と、御本殿の絵柄が入った御朱印。
更に松阪神社では、月替わりの御朱印も頂けます。3〜5月は桜、6〜8月は朝顔、9〜11月は紅葉。お正月には、500枚限定の御朱印もあります。
➁本居宣長ノ宮|全国から参拝者が訪れる学業成就の神社
続いて紹介するのは、松阪神社から徒歩1分の「本居宣長ノ宮」です。

本居宣長といえば江戸時代を代表する国学者です。
「古事記」の注釈書である「古事記伝」を35年かけて完成させた研究熱心な姿から、本居宣長ノ宮には学業成就を祈る学生さんが訪れるそうです。人気のお守りは、やはり合格御守。

こちらで頂く御朱印は、御朱印を紹介する本にも多数掲載されており、全国から御朱印が目当ての参拝者も訪れます。

絵馬を掛けに行くと、高校合格、大学合格、国家試験合格、資格の合格など切なる願いの数々。

本居宣長ノ宮から徒歩5分のところには松坂城跡があり、そこから御城番屋敷を眺めるのもおすすめです。

▲城跡の麓に見える御城番屋敷
松阪の市街地は戦時中に空襲がなかったので、今も昔の街並みが綺麗に残っています。
③御厨(みくりや)神社|三井グループ、あずきバーの井村屋も!?
最後に紹介するのは「御厨(みくりや)神社」です。

▲御厨神社の本殿
御厨とは、御(神の)厨(台所)を意味し、米や麦、魚などの食材をここに集めて、伊勢神宮に奉納されていたそうです。そのため、食材の神様としても参拝される方もいます。
こちらが御朱印です。

御厨神社には本殿の近くに、3つの境内社があります。順番にご案内します。
まず、赤い鳥居は、髙春稲荷神社。

あずきバーや肉まん・あんまんでお馴染みの井村屋製菓の守り神です。
そのお隣にあるのが、大山祇神社。

松阪市魚町にある旧長谷川治郎兵衛家の守り神です。長谷川家は松阪を代表する豪商であり、松阪木綿で大成功をしました。
最後に、赤い格子がお洒落なお社は「三圍(みめぐり)稲荷神社」です。

こちらは三井グループ、三井家祖先の祈願神社。江戸時代、松阪に生まれた商人三井高利は店先売などの斬新な商法を用い、三井グループの基礎を築いた人物です。
御厨神社はそのバイタリティと、神社へのお参りを大切にされてきた歴史文化を感じる場所です。
御朱印巡りはリセットする時間
神社の凛とした空気は気持ちよく、宮司さんが書いてくれる御朱印の筆先は美しい。みなさんも松阪市で御朱印巡りをして心をリセットする体験をしてみてはいかがでしょう。
【取材】
2022年2月
【取材ご協力】
・松阪神社
松阪市殿町1445
tel 0598‐21-3689
・本居宣長ノ宮
松阪市殿町1533番地2
tel 0598‐21-6566
・御厨神社
松阪市日野町690
tel0598‐21-0861
三重県松阪市は日本のほぼ中央に位置し、世界に誇るグルメ・松阪牛、豊かな歴史文化、美しい自然を楽しめます。江戸時代、お伊勢参り(日本最高位の神社への巡礼)の最後の宿場町であった松阪は、多くの人やものが行きかう交通の要衝として栄え、多数の豪商を輩出しました。これらの商人たちが、江戸で松阪もめんなどの商いに成功し、松阪に繁栄をもたらしました。