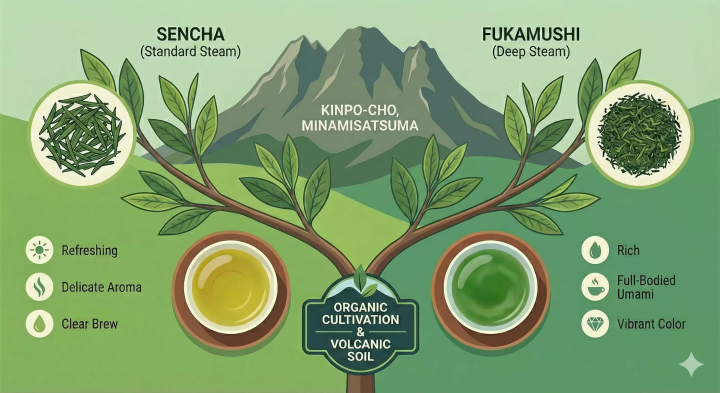【2025-26】日本の冬。12月〜2月の行事とまつりを体験しよう!

日本には伝統的な行事やまつりがたくさんあります。今回は、冬(12月、1月、2月)に行われる行事や特徴的なまつりをご紹介します。ぜひ日本観光の際に日本の文化や風習に触れてみてください。
日本の冬の行事やまつりを体験しよう!
日本の冬は、12月〜2月にあたります。日本列島は南北に長い地形のため、冬でも暖かい南の島から、大雪に見舞われる北の地方まで、天候はさまざま。
とはいえ、年末年始をはさむこの季節には、冬ならではのまつりや行事、食べ物が楽しめます。そのうちのいくつかをご紹介しましょう。
目次:
12月のまつりと行事
大晦日

日本では、月の最後の日を「晦日(みそか)」、1年の最後、12月31日のことを「大晦日(おおみそか)」と呼びます。
新年の準備で忙しい日ではありますが、ひと息ついた夜、多くの人は家族いっしょに「年越しそば」を食べ、新しい年を迎えます。この習慣には、そばのように「細く長く」という延命長寿の願いなどが込められています。
各地の神社や寺院では、年越しの行事が行われます。神社の境内では、神に奉仕する長である神主(かんぬし)が夜を徹して火を焚き、罪やけがれ(心身が清らかでない状態のこと)を清める「大祓(おおはらえ)」を行います。
寺院では僧侶が、深夜0時をはさんで、108回「除夜の鐘」をつきます。この「108」という数字には、1年を表すという説や、人間の煩悩(※1)の数という説などがあります。
※1:煩悩(ぼんのう)……仏教用語。人間の心身を悩まし、苦しめ、煩わせ、けがす精神のはたらき。
あわせて読みたい
なまはげ

秋田県男鹿市や潟上市などでは、大晦日の晩に「なまはげ」と呼ばれる鬼が家々を訪ねて回る民俗行事があります。
じつは、この鬼、地元の男性たちが扮しています。大きな鬼の面をかぶり、包丁などを持った恐ろしい姿で、「悪い子はいねぇがー(いないか)」などと言いながら家々を訪れることで、悪心を戒めたり、厄払いを行っているのです。
同じような行事は、青森県や岩手県、新潟県、石川県など、寒い地方に広く分布していますが、もっとも有名なのが秋田県。大晦日のほかにも、毎年2月には「なまはげ柴灯(せど)まつり」と呼ばれるなまはげに関する大きな行事が行われています。
【なまはげ柴灯まつり】
日時:2026年2月13日(金)・14日(土)・15日(日) 18:00~20:30
詳しくは、なまはげ柴灯まつりの公式HPをご確認ください。
あわせて読みたい
1月のまつりと行事

「正月(しょうがつ)」とは1月の別名で、その年の作物を豊かに実らせてくれ、家族が元気で暮らせるように守ってくれる年神様(としがみさま)を迎える行事のことでもあります。
現在は、1月1日〜3日までを「三が日」、7日までを「松の内」と呼び、この期間を「正月」ということが多いですが、20日までを正月とする地方もあります。
「正月」は、日本の行事の中でも最古と言われ、数々の風習が今も引き継がれています。たとえば「正月飾り」もその1つ。家のなかには、年神様への供え物として丸い餅を重ねた「鏡餅(かがみもち)」。
玄関には藁で編んだ「注連縄(しめなわ)」と呼ばれる、年神様を迎えるのにふさわしい神聖な場所であることを示すための飾りをします。

年が明けて初めて社寺にお参りすることを「初詣(はつもうで)」といいます。
初詣は、神社でも寺院でもどちらでもよいとされ、とくに、「明治神宮(東京都渋谷区)」や「伏見稲荷神社(京都市)」、「川崎大師(神奈川県川崎市)」などは、毎年、テレビニュースに出るほど、多くの参拝客が訪れます。

正月は、餅(※2)の入った「雑煮(ぞうに)」という汁物とともに「おせち料理」を食べます。
おせち料理は、元々「節供(せちく)」という、年神様への供え物で、かつては、各家庭で手作りされていましたが、最近は市販品を買う人も増えています。
正月の挨拶は、「あけましておめでとう」という言葉です。新年、初めて出会った人同士はこの挨拶を交わします。正月に日本に滞在されているなら、ぜひ使ってみてください。
※2:餅(もち)……もち米を蒸して、米粒がなくなるまで押しつぶした、日本の伝統食品。
七福神詣(しちふくじんもうで)

「七福神」とは、福をもたらす七体の神です。七福神詣とは、正月に七福神が祀られている社寺に参拝し、七福神を一巡することで、その年の福徳を祈願する習慣があります。
たとえば、毎年1月の第二月曜に、京都市東山区の「泉湧寺」では、境内の各寺院に祀られている福神が一般公開され、全国から多くの人が集まります。それぞれご利益が異なる、個性的な7人の神様にお参りして、福をいただきましょう。
あわせて読みたい
十日えびす

「十日えびす」とは、毎年1月10日とその前後の9日と11日に行われる、えびす神社の祭事です。
七福神のひとり「恵比寿(えびす)」が祀られている神社は、大阪・兵庫・京都などの関西が中心。釣竿と鯛を持ってふくよかにほほえむ神様は「えべっさん」と親しみを込めて呼ばれています。
祭事でもっとも有名なのは、大阪市の「今宮戎(いまみやえびす)」で、100万人を超える参拝者が商売繁盛を願って訪れます。
2月のまつりと行事
節分

「節分せつぶん)」とは、季節を分ける日という意味で、昔は春夏秋冬すべての季節の初めをそれぞれ節分といっていましたが、今は春だけを示しています。
節分は毎年2月3日ごろですが、2021年は124年ぶりに2月2日が節分でした。2026年は2月3日が節分の日です。節分には、邪気をはらう伝統行事として「豆まき」を行い、伝統的なお寿司「恵方巻き」を食べます。
豆まきは、煎った大豆を木でできたマス(日本古来のコップのようなもの)に入れて、「鬼は外、福は内」と声をかけながら豆をまきます。恵方巻きは、無病息災や商売繁盛を象徴した通常よりも長い巻き寿司を、特定の方角を向いて食べる風習があります。2024年の恵方(その年の縁起のよい方角)は、「西南西」です。
千葉県の「成田山新勝寺」では、毎年節分に、大相撲力士やタレントなどが豆まきをすることで知られています。
あわせて読みたい
さっぽろ雪まつり

北海道札幌市では、毎年2月初旬に「さっぽろ雪まつり」が開催されます。
2026年2月の第76回さっぽろ雪まつりは、さっぽろ雪まつりの象徴である大雪像5基を中心に、中小雪像と、雪体験アトラクションコンテンツを展開!
伝統的なまつりや行事は、その場に身を置くだけでも日本の伝統文化を肌で感じることのできる絶好のチャンス。この機会にぜひ体験してみてはいかがでしょうか。
【2026さっぽろ雪まつり】
日程:2026年2月4日(水)〜11日(水・祝)
詳しくは、さっぽろ雪まつりの公式HPをご確認ください。
※本記事は2015年12月27日に公開した記事を2024-2025年版にリライトしました。
All pictures from PIXTA