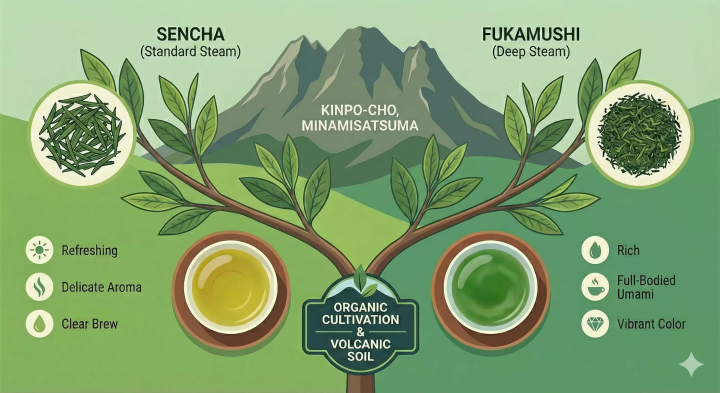【2025】日本の夏祭り・夏の行事を体験しよう!6月~8月の伝統行事をまとめて紹介

日本には伝統的な行事やお祭りがたくさんあります。今回は、夏(6月、7月、8月)に行われる行事や特徴的なお祭りをご紹介します。ぜひ日本観光の際に日本の文化や風習に触れてみてください。
年々暑さが増すと言われている日本の夏ですが、夏ならではの楽しみがあるのは、昔から変わりません。
7月1日には、富士山をはじめ、夏の一定期間だけ開山する山の「山開き」の神事が行われ、夏のレジャーシーズンが始まります。
6月〜8月の暑さを楽しむお祭りや行事を体験してみてください。
目次
1.6月の行事
2.7月のお祭りと行事
3.8月のお祭りと行事
4.お役立ち情報
6月の行事
梅雨入り

「【2024最新】日本の「梅雨」の期間とは?梅雨入り・梅雨明けの時期を地方別に解説!」より
梅の実が熟す頃に雨が降り続くということで、毎年6月10日前後は「梅雨入り(つゆいり)」と呼ばれています。ここから約1カ月間は「梅雨」という雨季です。
観光には不向きと思われがちですが「梅雨晴れ(つゆばれ)」と呼ばれるような一時的に晴れることもありますし、「空梅雨(からつゆ)」と呼ばれる、雨量の少ない年もあります。
また「梅雨寒(つゆざむ)」と言って、季節はずれの寒さに見舞われることもあるので、日々、天気予報のチェックをお忘れなく。
あわせて読みたい
7月のお祭りと行事
七夕

「夏の京都で小粋な夕涼み。貴船神社七夕笹飾りライトアップの見どころ〜」より
「七夕(たなばた)」は、中国の星伝説と宮中行事が結びついて、日本独特の行事となりました。神様に引き離された、ひこ星とおり姫(※1)の夫婦が、1年に1回、7月7日だけ、空の天の川(※2)を渡って会うことが許されるという、ロマンティックな伝説に基づく行事です。
家庭では、笹竹に、飾りやさまざまな願い事を書いた短冊(たんざく)という紙を下げ、願いを込めながら星空を見上げます。

太陰暦で7月7日にあたる8月7日前後に「七夕まつり」として、豪華な飾りが有名な「仙台七夕」(宮城県)、浮世絵や美人画が描かれた大小数100百の絵が夜空を艶やかに彩る「七夕絵どうろうまつり」(秋田県)など、各地で美しい七夕まつりが行われています。
※1:ひこ星とおり姫……ひこ星は「わし座のアルタイル」、おり姫は「こと座のベガ」を指すと言われている。この2つに「はくちょう座のデネブ」を加えた3つ星座を結んで、「夏の大三角形」と呼ばれる。
※2:天の川(あまのがわ)……晴れた夜空に帯状に見える無数の恒星の集まりで、日本では、夏から秋に最もよく見える。
祇園祭
祇園祭(ぎおんまつり)は、9世紀から続く八坂神社(京都市東山区)の伝統的な祭礼。毎年7月1日から1カ月間に渡って行われる、日本を代表するお祭りとして知られています。

「【2024最新】日本三大祭りの1つ「祇園祭」ガイド!日程・見どころは?各日の行事、アクセスなどを徹底解説!」より
最大の見どころは、ユネスコ無形文化遺産にも選ばれた「山鉾巡行(やまぼこじゅんこう)」。17日の「前祭(さきまつり)」と24日の「後祭(あとまつり)」に分かれて行われ、前祭では23基、後祭では10基の山鉾が京都市内を練り歩きます。
「山鉾」とは、神社の祭礼に引かれる屋台の飾り物のことで、祇園祭の山鉾は、旧家や老舗が持つ宝物が披露されるため、「動く美術館」とも言われています。
【祇園祭2025の日程】
祇園祭2025は、2025年7月1日(火)〜7月31日(木)で開催予定です。
●宵山(前祭):7月14日(月)~16日(水)
●屋台露店:7月15日(火)~16日(水)
●宵山(後祭):7月21日(月)~23日(水)
●山鉾巡行(前祭):7月17日(木)
●山鉾巡行(後祭):7月24日(木)
あわせて読みたい
隅田川花火大会

「隅田川花火大会が開催!日程・最寄り駅・穴場鑑賞スポットをまとめて紹介」より
7~8月は、各地で花火大会が開催されていますが、なかでも、「隅田川花火大会(すみだがわはなびたいかい)」は、全国的に有名です。東京の浅草や向島周辺に近い隅田川沿いの河川敷で、毎年7月の最終土曜日に大勢の見物客でにぎわいます。
時間帯は、午後7時すぎから1時間半。会場は、第一会場(桜橋下流~言問橋上流)と第二会場(駒形橋下流~厩橋上流)の二カ所で、合計約2万発の花火が打ち上げられます。第一会場では、創作花火のコンクールも行われるため、珍しい花火を見ることができます。
【隅田川花火大会2025の日程】
●日程:2025年7月26日(土)
●打ち上げ時間:第一会場19:00〜20:30 約9,350発 (桜橋下流~言問橋上流) / 第二会場19:30〜20:30 約10,650発 (駒形橋下流〜厩橋上流)
●詳細:隅田川花火大会の公式HPをご確認ください。
●備考:天候よっては、順延や中止になることもありますのでご注意ください。
あわせて読みたい
土用の丑の日

古代中国の暦で、夏の「土用(どよう)の丑(うし)の日」にあたる日に、日本ではたんぱく質やビタミンが豊富で夏バテに効くウナギを食べる風習があります。
ウナギは、身を開いて甘じょっぱいタレをつけながら焼いた「蒲焼(かばやき)」を、白米にのせる食べ方が一般的。
「土用の丑の日」は、太陽暦に基づいていないので年によって微妙に日時がずれ、2025年の土用の丑の日は2回あります。「一の丑」は7月19日(土)、「二の丑」は7月31日(木)です。あちこちのウナギ屋から、香ばしい蒲焼の香りが漂ってくることでしょう。
8月のお祭りと行事
お盆

「【夏】あの人がこの世に帰ってくる4日間。日本の「お盆」とは」より
お盆とは、祖先を祀る夏の行事。祖先の霊がこの世に戻ってくると言い伝えられています。
お盆の期間は、主に東京では7月13日~16日の4日間、そのほか全国の地域では8月13日~16日とされています。地域によって時期は違うようですが、この短い期間にだけ、ご先祖様の霊がこの世に戻ってきます。
そして、ご先祖様が無事にこの世に戻り、また安心してあの世に帰っていけるように、お盆の期間にはさまざまな準備をするのです。
阿波おどり

「阿波おどり(あわおどり)」は、徳島県を発祥とする伝統芸能の1つです。約400年の歴史があり、夏季には県内だけでなく日本各地で開催されていますが、最大規模を誇るのは「徳島市あわおどり」です。
ここで開催されるのは、毎年8月12日から15日までの4日間。期間中、約130万人の見物客、約10万人の踊り手が訪れると言われるほど、徳島市の中心街一円は踊りの渦に巻き込まれます。
「連(れん)」と呼ばれる踊り手のグループが多数あり、それぞれに工夫を凝らした衣装や踊りを見せてくれます。最近では、見ているだけでは物足らず、踊りに飛び入り参加する訪日観光客の姿も増えているそうです。
【徳島市あわおどり2025の日程】
●日程:2025年8月11日、12日、13日、14日、15日(11日は屋内オープニングイベント)
●場所:Sansan藍場浜演舞場、あわぎん南内町演舞場、両国本町演舞場など
●詳細:阿波おどりの公式HPをご確認ください。
あわせて読みたい
京都五山送り火・嵐山灯篭流し

Photo by Pixta
「京都五山送り火(きょうとござんおくりび)」は、毎年8月16日の夜に、死者の霊を送るために、京都を囲む5つの山に火が灯される、伝統的な仏教行事です。
火は、午後8時から、それぞれ「大文字」「妙法」「船形」「左大文字」「鳥居形」の順番で灯され、30分間、暗い夜空に幻想的に浮かび上がります。

Photo by Pixta
また、渡月橋下流の嵐山中之島公園では、先祖の霊を敬う「嵐山灯篭流し」も行われます。川面を流れていく灯篭が幻想的な幽玄な世界観は、この時期しか見られない貴重な光景です。
あわせて読みたい
お役立ち情報
MATCHAでは、日本の観光を楽しむ際に役立つ情報を、ほかの記事でも紹介しています。ぜひ、こちらもあわせてチェックしてみてください!
・コンビニで外貨から日本円へ両替する方法
・ホテルで使える簡単な日本語フレーズ
・外国人観光客向けの便利なWi-Fiサービス
あわせて読みたい
本記事は、2018年12月に公開された記事をリライトしたものです。